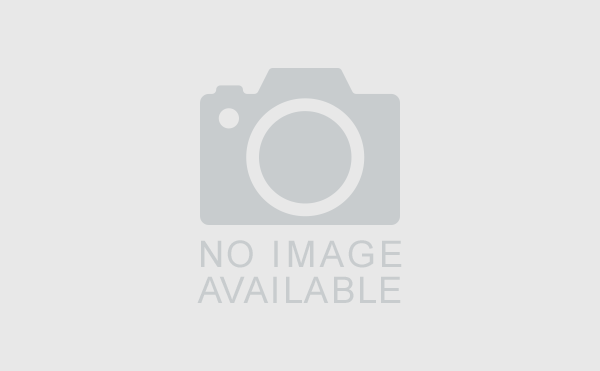Report11<KANSAI>
日本初、放送システム全体をIP化し稼働開始
~開局以来はじめての社屋移転~ テレビ大阪
テレビ大阪(TVO、大阪市中央区大手前、品田卓代表取締役社長)は2024年5月13日、1982年3月の開局以来、初めて社屋を移転。放送システム全体としては日本初のIP化を実現し、稼動を開始した。新社屋は、旧社屋東隣の日本経済新聞社旧大阪本社跡地に、日本経済新聞社(日経)と大和ハウス工業が事業主体となり進めていた「大阪・大手前一丁目プロジェクト」の複合ビル(地上21階・地下1階・塔屋1階、延べ床面積38,776.63㎡)として完成。1階~4階にTVO、6階~20階にホテル「ダブルツリーbyヒルトン大阪城」が入る。

周囲には水都大阪を象徴する大川、寝屋川が流れ、大阪城の外濠や大阪城公園への入り口はすぐそこ、という場所に位置することを活かし、天満橋駅と大阪城公園を結ぶ動線部分には、遊歩道空間としてリバーウォークと多目的広場が整備。新社屋1階にはエントランスホールと、イベント開催や公開収録などができ、にぎわいの拠点となるような多目的ホールを設けた。
一方、放送設備は、全面的にIP技術を採用。最新の設備を導入し、効率的な運用を可能とした。そのうち、マスターシステムは、TXN系列内で更新時期の近い4局(テレビ北海道、TVO、テレビせとうち、TVQ九州放送)共通仕様となるIP方式を採用。TVOは4局目の運用開始となったが、将来の4K放送やインターネット同時配信など、サービスの多様化に柔軟に対応できる拡張性の高い設備が整った。加えて、従来のSDIベースではなく、全館をフルIP・ファイルベースで構築するという、日本初のチャレンジングな取り組みも行った。
今回のレポートでは、新社屋への移転で導入が実現したIP放送設備の特徴や運用状況、今後の課題などについて、TVO技術局長・芳田浩一氏、TVO技術局 技術部長・齊藤智丈氏に話を伺った。併せて、にぎわい創出と、“LINK MORE”をコンセプトにフリーアドレスを採用し、部署間の連携強化を目指す新社屋の特長や活用状況などを紹介する。

一番最後になるよりは、一番先頭になろう
本 紙 : 社屋移転の経緯を教えてください。
TVO : 開局から40年を過ぎ、建物の老朽化が主な移転理由です。移転構想が立ち上がったのは2015年でした。当初から旧社屋に隣接する現在の場所へ移転するという構想ではなく、候補地は何か所かありました。そんな中、日経大阪本社が移転されました。そのタイミングで日経グループの当社も同じ場所へ移転できればベストだったのですが、スペースが足りなかったため、同時移転は叶いませんでした。最終的には、日経旧大阪本社跡地に、ホテルと同居する形で移転するという経営判断が下されました。
本 紙 : 放送システム全体のIP化、系列4局共通仕様のIPマスターはどのようにして実現したのですか?
TVO : 2019年に新社屋計画が正式にスタートしました。その時期でも単独か複合型かは議論中でしたが、放送設備に関しては合理化、省力化を見据え、当時の経営陣が「オールIPで構築する」という目標を立てていました。
マスターの仕様を4局で共通化する検討は、新社屋計画のスタートと並行して進んでいました。前回から約12年ぶりとなる更新のタイミングが2024年だと考えた場合、IP化が進んできた頃になります。従来型のSDIマスターで更新すれば最後のSDIマスターになると予想されました。一方、IP化すると最初の放送局になる。どちらを選ぶかを話し合い、「一番最後になるよりは、一番先頭になろうよ」と、マスターのIP化は早々に決定していました。
送出設備であるマスターがIP化されれば、放送設備のフルIPも将来的にはあり得ます。それでは他の部分はどうするか?当時の技術局長がその将来像について話をしたところ、トップダウンでフルIPが決定した、というのが当社のケースです。この決定には、当時の技術局長も「本当に!?」と驚いたと聞いています。新社屋へは毎週のように他局から見学に来られますが、「フルIP決定までのボトムアップはどうされたのですか?」とよく尋ねられます。(笑)
当時は、まだまだIPの実績も情報もなく時期尚早ではないかというのが正直な感想でしたが、完成した今から考えると、将来の世代に何を残すのかをきっちりと考えて決断してくれた。経営陣の英断だったと思う次第です。
速報の自動化を開発で、省力化とミス軽減
本 紙 : マスターの特徴を教えてください。
TVO : マスター室は、監視室内の設備や什器を最小限にして軽量化。状況把握やコミュニケーションを行いやすいレイアウトになっています。旧社屋では点在していたラック室、サーバー室を1か所に集約し、将来の拡張スペースを確保しました。また、各エリアのゾーニングを強化し、動線や業務環境の改善を図りました。
新社屋は、マスター・回線を含め設備の詳細を決めていく段階で出始めたST2110ベースで運用しています。素材伝送は、MoIPとファイルベースがメインとなります。
4局共通仕様としては、速報の自動化を開発しました。キー局から配信されるニュース速報を送出する尺が番組にあるかどうかを、自動で判断して送出します。省力化になることと、タイミングをオペレートする際のミスがなくなります。
効率面では、テレビ北海道が開発された「バーチャルマスターオペレーター」の一部を使いました。これまでマスターは、様々な装置を監視制御するためのパソコンだらけでした。どの端末に向かい合ってどのような作業をするかという習熟には時間がかかっていましたが、操作すべき端末のディスプレイが自動で切り替わり、それに合わせて操作すればよくなりました。
また、当社とTVQ九州放送の共通仕様として、収録とプレビュー機能に特化した「放送準備システム」を導入しました。IPファイル化した素材を転送して送出に備えられます。

スタジオ減もIPで柔軟な制作環境に
本 紙 : スタジオなどはどのように変わりましたか?
TVO : 旧社屋には3つのスタジオと3つのサブがありました。移転にあたり、これまでの稼働率から鑑みて、減らしても運用できるのではないかとの判断から、スタジオとサブは2つずつになりました。IPスタジオサブシステムになればクロス運用が可能で、スタジオサブが減ったことにも対応できるようになります。
スタジオの仕様も、ホリゾントはなく照明バトンも下りない。従来のようなスタジオではなくスタジオっぽくして使うようなものにしました。今までのような保守管理に費用がかかるスタジオではなく、簡易なスタジオでバーチャルなセットを使った番組制作に方向転換すればいい、という判断です。

本 紙 : IPを活かしたスタジオ運用について教えてください。
TVO : 通常は1スタと1サブ、2スタと2サブを紐づけますが、クロス運用では、1スタと2サブ、2スタと1サブを紐づけます。両サブの設備は、クロス運用に対応しやすいように基本的に同一にしました。スイッチャーもミキサーも同じものを入れて、どちらも同じようにオペレートできます。また、どのサブでスタジオカメラを使用しているかを個別に表示するランプを設置しています。
ただ、スタジオの広さには違いがあります。1スタは大型特番にも対応できる広めのスタジオ、2スタはほぼトーク番組向けの狭い作りになっています。
普段は、報道のニュース番組が1スタを使います。特番などで報道以外が1スタを使いたい場合には、報道のニュース番組が2スタに逃げ、サブは1サブのままでクロス運用します。サブを1サブのまま使う理由は、報道部の隣にあり、移動距離が短い方が緊急案件に対応できるためです。
現在、非常に効率よく運用できており、現場からは思いのほか「クロス運用を行いたい」という声が上がっています。


設計段階から工夫、スムースな運用を実現
本 紙 : ほかにIP化のメリットを感じていることはありますか?
TVO : 年に1回の大型特番などのセッティングにおいて、人手、時間、手間がかなり削減できています。ベースバンドではケーブルの引き回しなどにかなり時間がかかっていましたが、IPではプリセットで覚えさせておけばボタン一つで呼び出せます。また省力化は、IP化したことに加えて、1階の多目的ホール、5階のテラスでも中継や番組制作ができるようにするという、事前設計プランによるところも大きいです。
当社では毎年7月に『天神祭生中継』を放送しており、新社屋5階のテラスは、この生中継を想定して設計しました。移転して初めての大型特番が、40回目を迎えた『天神祭生中継』。サブには映像、音声、インカムの各メーカーさんに待機してもらっていましたが、トラブルなく非常にスムースにオンエア終了まで運用できました。
本 紙 : 1階の多目的ホールを活用した事例を教えてください。
TVO : 多目的ホールでは、7月にテレビ東京『開運!なんでも鑑定団』の「出張鑑定団in大阪」の収録を実施しました。2001年に放送をスタートした『きらきらアフロ』の最終回の収録も行い、9月、当社が番組を制作した時代に作ったポスターやグッズ集めた『きらきらアフロ展』を2週間にわたって開催しました。
8月には、『初耳怪談』発の2つのイベント、『心霊写真展』と有料トークライブ『大阪夏の怪』を開催しました。9月に実施した『日経スペシャル もしものマネー道 もしマネ』の初めての公開収録は、自社制作番組としても初めての公開収録となりました。
新たにできた多目的スペースは、番組収録だけではなくイベントでも使え、新社屋のコンセプト“LINK MORE”の一環としてにぎわい創出に貢献できていると感じています。
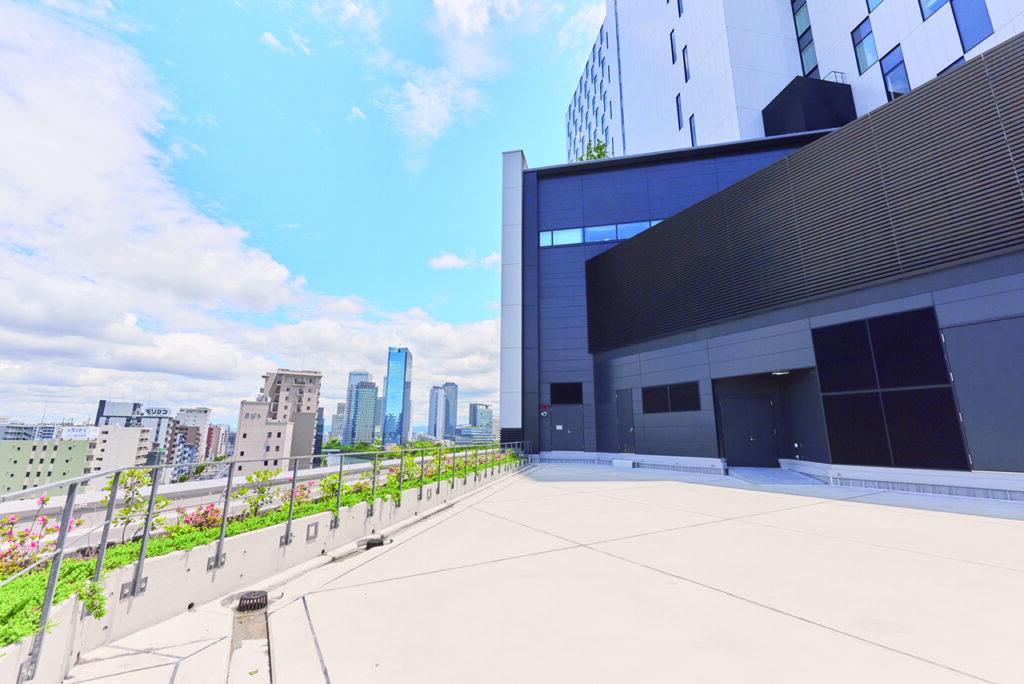
-1024x682.jpg)

IP人材育て、さらなるコンテンツ発信を
本 紙 : 稼動して約半年。新設備を使ってみていかがですか?
TVO : 当社の特長として、Panasonic Kairos Core 1000というIPネイティブスイッチャーを入れています。コロナ禍でリモート出演が増え、ワイプの小窓を重ねていくことが多くなりました。今までのベースバンドでは枚数に制約がありましたが、いくらでもワイプを重ねられます。これからは、大阪まで来てもらえない演者の方に、遠方からリモート出演してもらうような番組作りがよりできていくのではないかと思っています。

IPとは違った話になりますが、新社屋への移転によって設備を一新できたことで、旧社屋にはなかったバーチャル装置を導入しました。フルバーチャル番組が増えてきている中、当社も取り組みを進めていこうという方針で、報道、制作陣からは「新しいことができるようになった」と喜びの声が届いています。
一方、心配していたのはIP化による遅延です。レギュラー番組としてニュース番組とトーク番組は制作していますが、音楽番組は制作していません。『天神祭生中継』のゲストによる歌唱でどの程度、遅延による影響があるのかを心配していたのですが、問題なく運用できたと報告を受けています。稼動してみれば慣れの部分もあり、ネックにはならなかったと感じています。
「いずれSDIはなくなり、これからは遅延はあるものとして番組作りをしていかなければいけない」とずっと言ってきていました。当社にとって、早くから遅延に慣れていくことができるのはメリットだと思います。
本 紙 : IPに対応できる人材育成やトラブル対策なども必須だと思います。
TVO : IPサブを運用するうえで、IPに関する最低限の知識は必要だと思いますが、知識もオペレートの習熟度も人それぞれ。オペレーター全員が一から勉強することも難しいので、設計段階で、なるべくこれまでのベースバンドと同じような操作感で操作できるようにしました。しかし、IP機器を増設するとなると、IPネットワークの設定が必要になります。アドレスが重複したりしていると、たちまちすべてが動かなくなります。現在、設計段階で対応できるようにしていますが、IPの知識は、これからみんなに深めていってもらわなければなりません。
また、IP構築前に一番心配だったのは、Media over IP。大規模中継時にストリームが耐えられるかどうかに気を遣いました。仕様は『天神祭生中継』での流量を想定して決めて設計・テストを行いました。実際に生中継をしてみると、流量は想定より少ないぐらいで安心しました。一番たくさんの負荷がかかる大規模中継時に余裕を持って乗り越えられることが分かったので、この先もっと大きな番組を制作しても問題ないことが確認できました。
IPシステムを構築する仕様決定前には、シスコシステムズさんに協力を得て、みっちり勉強会を行いました。仕様に関わる主要メンバーが約6か月間、1週間に丸2日の研修を受けました。座学から、最終的には旧社屋スタジオで一から構築する体験まで、技術と運用のメカニズムを理解しました。
『天神祭生中継』での運用の際、これまでIPに関して知識が全く伴っていなかった者が、ネットワークスイッチを監視する画面を確認して状態の把握に努めているという姿を見て、IP運用が浸透していってくれていると感じました。この調子で展開していけるようにしていきたいと思っています。
本 紙 : 今後の取り組みについて教えてください。
TVO : まず、技術の習得。IP知識を身につけてもらうための研修を進めていきます。今のところ、IPに関してはノートラブルですが、トラブルが起こったときにどう対応できるかは今後の課題です。起こりうることを見越してトレーニングをしていかなければならないと思っています。
番組制作では、フルバーチャルに対応して狭い方の2スタを活用できるような番組作りを目指していきます。将来的にはIPの利点を活かし、リモートプロダクションもやっていかなければならないと思っています。
本 紙 : ありがとうございました。